
みなさんは昨日どれくらいの野菜を口にしたでしょうか?
食べた野菜はどこで生産されたものでしょうか?
こんにちは!
野菜ソムリエプロ・やすながひろきです
当Blog『にっぽん旅やおよろ寿』では
・地元の農産物の発信
・地域内でご活躍される生産者さんの発信
これらを通して地域の皆さんと生産者さんをつなぐことを目的にしています
また
・健康情報
・地域の魅力
などなどもお届けします
1日分の野菜350gのわけ
冒頭の質問の1つ目「みなさんは昨日どれくらいの野菜を口にしたでしょうか?」へと戻ります
野菜にはビタミン類・カリウム・食物繊維など、ご飯やお肉類・魚類ではなかなか摂ることのできない栄養素が多く含まれています
これらの野菜に含まれる栄養素は
1.三大栄養素(炭水化物・たんぱく質・脂質)の効率の良い吸収・代謝を促す
2.身体の免疫力の向上や機能維持など身体を調整する働きを持つ
3.ほかの栄養素の働きをサポートする
などさまざまな働きをしてくれます
野菜の品目(種類)によって含まれる栄養素は違ってくるので
・緑黄色野菜(人参やほうれん草など)なら230g
・淡色野菜(白菜やキャベツなど)なら120g
合わせて350gを1日分の野菜摂取量の目安として設定されました
国内産野菜と外国産野菜
冒頭の質問の2つ目「食べた野菜はどこで生産されたものでしょうか?」についてです
みなさんは野菜の原産地や生産地の表示をよく見ると思います
「国内産野菜は価格が高い」
「外国産野菜いわゆる輸入野菜は価格が安い」
と思われたことはないでしょうか?
価格の差は
・生産コストや生産量の違い
・栽培されてから店頭に並ぶまでの仲介マージンの違いなど
で生じます
買い物する側にとっては価格の安い方がいいですが実は外国産野菜は不安定な要素を含んでいます
アメリカのトランプ大統領の提唱したような関税政策や円高・円安などによって輸入コストが変動した場合、店頭に並んだときの価格も変わってくることがあります
また生産量によっては日本に輸入されなくなる場合もあります
当たり前に買えていたものがある日突然買えなくなってしまうと言った可能性があります
また別の視点で見てみましょう
日本は遺伝子組み換え食品や使用される農薬などに対して厳しく規制することで外国産野菜の安全性を確保しています
ですが外国産のもので「この野菜を栽培している農家さんってどんな人?」と考えたとき遠く離れた国の農家さんを知ることは難しいでしょう
地産地消を応援するわけ
地産地消の定義は「地域内で生産されたものをその地域内で消費する」ことです
農産物の分野に立ってみると
1.地域内なので生産者さんの「顔が見える」
2.出荷コストを抑えられるので環境にも配慮されている
3.地域のものを食すことでその地域を応援している
これらのことが地産地消の魅力だと私は考えています
また「地産」の範囲を農産物だけではなく広く一次産業で生産される食品全般と考えたとき、生産者さんは「地域を育んでいる」と言う意識・生活者さんは「地域のもので育った」と言う意識が芽生えて、地域の活性化に対して精神的な支柱になるものだとも私は考えています
まとめ
1.野菜には野菜にしか摂れないさまざまな栄養素があるので1日350gが推奨される
2.外国産野菜は不安定な要素を含んでいる
3.生産者さんの「顔が見える」地産地消
これから地産地消からはじまる地域の活性化に従事・尽力します
野菜ソムリエプロ・やすながひろき

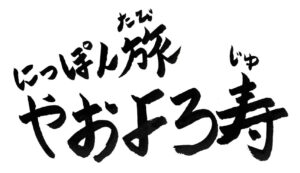

コメント